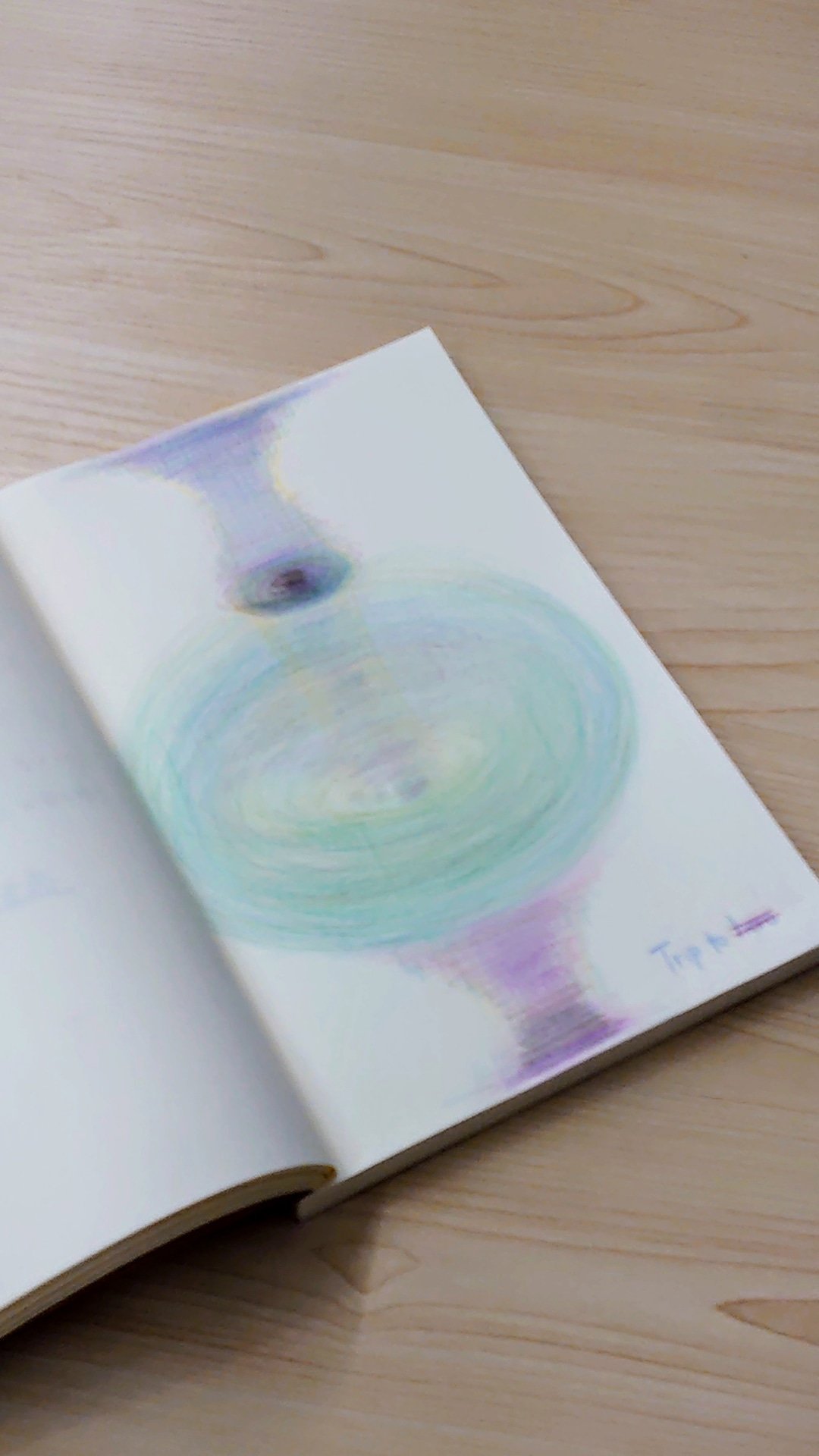260103 自宅にて
2025年は、1960~80年代の建築や著作の中にいる時間が多かった。
(極端な)早寝早起きをし、意識的に家に籠もる日をつくっていたこともあってか、潜伏しているという気分でもあった。そのなかで、研究している原広司を起点として、その交友関係から過去のテキストをさまざまに読み(これが膨大であった)、図面を見て、また自分のテキストや図面、模型に戻っていく。そんな日々であった。
また、いくつかの研究会に誘ってもらって顔を出した。そういう場には「今日においては〇〇を考えることが大事なのだ」という力強い主張と、それを示す手段としての建築、いわば宮内康がいう「アジテーションとしての建築」があった(宮内を読んだことは、60-70年代の動向をある側面から理解するうえで重要だった)。ただ、そうした傾向にはある種の緊張感があって、それに向き合いすぎると疲れてしまう、というのが正直なところだった。
あるいはそれは、「〇〇を考えないこと」と、いつか衝突し爆発する緊張感でもあるように感じていた。そうした感覚のなかで、最近出版された東浩紀の『平和と愚かさ』にはとても興味を持っている。年末年始のあいだに読むつもりだったが、まだしっかりと読めていない。とはいえ、経験による予感めいたものはあって、例えば、ヘーゲル的弁証法が不可避的に衝突(戦争)に行きつくのだとすれば、ひとつには矛盾を引き受けた原の建築思想、たとえば「非ず非ず」などに何かがあるのではないか、ということである。あるいは、ティモシー・モートンのいう「ゆるやかさ」はいかに可能か。
やや強引なところもあるが、今、自分が感じている緊張感は、60年代以降の動向と重なる部分があるのだろうか、などと想像する。特に去年の後半は、60-70年代のテキストを読みながら、時おり、そういうことを考えていたように思う。そういえば、柄谷行人は60年周期説のようなことを言っていた。また、カルチャーの周期は20年だと言われることがある。カルチャーは螺旋的な展開を持って良いような気がするし、20年前というのはアクティブな若年世代のなかにも実体験した過去として残っているだろう(今年、ORANGE RANGEが流行っているという話を何度か聞いたように…)。ただ60年前となると、体験されていない過去になる場合が多い。それは意識的に学ぶ対象であるように思え、去年取り組んだことのひとつだった。
それはそうと、そうしたある種の緊張感が問題を引き寄せ続けている、という感覚もある。あるいは逆に、身近にある問題の連なりが、緊張感をもたらし続けているともいえる。火種はいたるところ転がっている。同時代の動向として理解できる部分もあるのだが、身近な緊張感こそ適度に退けておく、棚に上げておくことも必要なのではないかとも思う。
そういう感覚から、ある建築の取り組みで「サスペンデッド」(suspended)なのだと言ったり、あるいは追々出す本に「能動的留保」や「待つこと」について書いたりしていたのだが、やや観念的であったかなと反省する。実務的に取り組んでいるのだし、今年はより実効性のある言葉や術を見つけ出したい。しかし、これもまた例の60年周期に近いのだが、磯崎らが論じた「不確定性」や「決定不可能性」は、(少しかたちを変えて)再登場しつつあるように思う。磯崎が「歴史の宙吊り(落丁)」としたのが68年からの20年間だということで、そういう時代にどう「展開」をもたらすことができるのか、70年代の殻から抜け出しながら考えていきたいことである。
さて、2026年は前々からひとつの区切りにしようと思っていた28歳の1年になります。
年度内には今取り組んでいる住居の改修がひと段落する予定で、そこからまた新しい仕事が始まりそうです。これまでやってきた仕事も引き続き。
なぜか機会をくださる方々に感謝し、がんばっていきます。
あれこれ書きましたが、去年に引き続き「Mind My Own Business」という感じでやっていこうと思いますので皆さま今年もどうぞよろしくお願いいたします。ご自愛ください。
敬愛する建築家の命日に
TALK : porous is not design but attitude
[TALK]
6月29日㈰に「porous is not design but attitude」という題で話します。会場は自分が改修に関わっている京都は木屋町のバー八文字屋です。ご予約不要、ワンドリンク制です。皆さん遊びに来てくれると嬉しいです。
内容としては、博論で取り組んでいるティモシー・モートンの環境哲学や原広司の建築論を起点に、村上春樹の小説やブラジルのカポエイラなどを巡り、多孔的であること、またアチューメントというあり方について、自身の設計活動を交えて広く浅く話すつもりです。が、状況に応じてあれこれ変えながらやると思います。
このブログに書き綴っていたことに対して、ある観点から全体性を与えるような試みでもあります。どうぞよろしくお願いいたします。
"porous is not design but attitude"
Date : 29 June 2025, 18pm-
Venue : ヤポネシアン・バー八文字屋
Speaker : 佐古田晃朗 Teruaki Sakoda
Graphic Design : Yuichi Nishimura / Rimishuna
Original Photo for Graphic : Gigi Wang
主催 : よるのかい
旅と偽り──欧州にて
なぜ旅に出るのかというと、脱出を求めているからだ。
普段は逃げ出したい場所にいる、というわけではない。ただ、日々を、そのルーティンを大切にすることと、そのルーティンから意識的に外れる術を持つことは、ともにあってこそ互いの価値を高め合うのだと思う。だからこそ、できるだけ毎日同じ場所で同じようなことを繰り返して、ときどきそこから脱出できるようにしておきたい。旅に出ることは、半ば強制的な脱出装置として働いてくれる。
たとえば、芸術家のシュシ・スライマンは、偽り(Fake)という言葉を用いて自身の制作活動を説明する。馴染みのない場所で、その馴染みのなさゆえに物事を新鮮に、あるいは慣習的なコンテクストの外側から見ることができる状態を総合的に表す言葉なのだと理解しているのだけれど、とてもよく表現されているなあといつも感心する。
彼女は、偽りであることは辛いことだけれど、場所の「本当」を理解することを助けてくれるのだと説明してくれた。そのときから、ときどき旅に出ようと思うのは、そうした経験を求めているからなのだとわかったような気がした。ガイドブックに従う模範的観光客のように振舞うことも、あるいはそうした観光客を表層的だと小馬鹿にし、どこまでも「深いところ」に入り込もうとする旅人のように振舞うことも必要としていなかった。何か明確に見たいものがあるわけではない。物事をどう見ることができるのかに期待していた (余談だが、こういうことを考えるときには、その昔に読んだジョン・アーリの『観光のまなざし』がとても役に立っている)。
だから、僕にとって旅に出るということは、偽り(Fake)の状態になろうとすることであると言えそうだ。あるいは、旅に出ることを通して、意図的に偽りの状態になれるよう練習することでもある。つまり、ルーティンが行われる世界の方に、偽りの感覚を持ち込みたいのだ。目新しいものの中に新しい何かを見出すよりも、見慣れたものの中に新しい何かを見出したいという考えがあって、偽りはそのために重要な感覚なのだと思っている。
そうしたことをどちらかというと観念的に考えてきた。2年前、同じように欧州を旅していたころには、このルーティンと脱出/偽りの関係は、固着性と多孔性の関係として捉えられていた。その後、尾道でシュシに出会って、自分の中での問題意識が少し明確になった。それで論文を書いたり、いくつか建築に関する実践に取り組んだりして、もう少しわかりそうになったところでまた欧州にやってきた。
といっても、旅の直前までバタバタと過ごしていて、こうした問いのことはすっかりと忘れてしまっていた(決して笑い事ではない)。ただ、毎日たくさん歩いているとだんだん大切なことを思い出してくる。歩けば何かがわかるということに、個人的で経験的な正しさを認めている。ときどき自分を歩かせないといけない。そういう自分への信頼は少しずつ堅いものになってきた。
それで今回の旅を通じて、この偽りの感覚を建築の空間へと昇華できる兆しが見えたように思う。緩やかな気付きで、20日ほど旅をした中で確か18日目の出来事だった。もちろん、きっかけは京都での日々の中にばらばらと散りばめられていたのだけど、旅先での実感が加わることで急激に何かが構築された感じがある。でももしそれがなかったら…と思うとゾッとするようなことでもある。打算的にならないようにしたいけれど、以前よりは時間の使い方とその効果に対して敏感になってしまう。
いつ以来か、高熱を出してしまい、向こう数日の予定をキャンセルしてしまった。今のうちにやっておきたいことはあったのだけど、それを嘆いても仕方がないので、大切だと思うことに今一度意識的になって、それを確かに思い出そうとしてみる。確かに思い出すということが大切だった。
猫やギロ・ピタ──アテネにて
3月、2年ぶりのアテネ。
20日ちょっとかけて欧州の都市をいくつか訪れようと考え、さも当然だというような感じでギリシャのアテネから始めることにした。旅する間の気候の変化や交通手段のことなどを少しは検討したのだけど、どうもアテネから始めるのが直感的にしっくりくる。それは、頭の中に世界地図──日本向けのメルカトル図法で描かれた世界地図──を思い浮かべてみると、日本からアテネへ、そこからドイツやスペイン、ポルトガルに行くのがどうにも適切なように思われるからかもしれない。日本から西へ西へ、大西洋に向かって進んでいくルートにある種の慣習的な妥当性を感じてしまう。2年前にも同じようなことを思った気がする。もしかすると地球儀を買った方がいいかもしれない。
2度目のアテネにやってきて思ったのは、多くの物事がほんとうには見えなくなってしまったということだった。うんうん、そうそう、そういう感じだよね、といった具合に浅薄な納得感が先行してしまう。もちろん予想はしていたのだけど、数年前の2週間程度の滞在でもそんな具合になってしまう。つい知っているのだという意識が働いてしまう。偽りの有効期限はとても短い。
ところで、アテネのまちにはたくさんの猫が存在している。猫にとって快適な場所なんだろう。飲食店はいたるところにテラス席を拡張していて、そこにはときどき物乞いをする猫や人間がやってきて僕らに声をかけてくる(あるいは落ちたものや残りものを持っていく)。もちろん、例の古代ギリシャ時代の遺跡の中にも猫たちは存在していて、当然「keep out」の掲示は全く意味をなさない。車もやってこなければ、遺跡をまじまじと見つめる観光客と、いったいいつまでかかるのか見当もつかない何かをしている研究者らしき人々ばかりの場所はきっと居心地がいいんだろう。それに、遺跡はたいてい日当たりがいいし。
ギロ・ピタというファストフードがある。ピタパンで薄切り肉をラップしたもので、どこで食べても大体おいしい。お肉はスブラキという串焼き肉の場合もあり、お店によっては玉ねぎやトマト、フライドポテトも一緒に包まれている。ソースにはヨーグルトと胡瓜でつくられるザジキソースが使われることも多く、さっぱりとしてとても美味しい。
色んなお店でギロ・ピタを食べることはギリシャでの楽しみの1つ。前回の旅では、クレタ島ハニアにある「Oasis」というお店で食べたギロ・ピタが一番気に入った。今回の旅では、アテネの街中にある「Kosta」という店で食べたスブラキ型の、それもザジキソースではなく胡椒を効かせた辛い味付けのものが一番気に入った。「ギロ」は薄切り肉というような意味らしいから、スブラキ(串焼き)型のものはもはやギロ・ピタではないのかもしれないけど、まあギロ・ピタということにさせてもらっています。確かにお店の看板には「Kalamaki Pita」と書いてあって、kalamakiは串という意味らしいのだけど、カルフォルニアロールだってお寿司だし、僕は中国人かもしれないから、ニーハオ。
「Kosta」にはアテネに滞在していた中盤に訪れた。最終日にも食べたいと思って行ってみると定休日だった。とても残念。それと「Kosta」にも住み着いているであろう猫がいた。定休日にはきっと横のお店でうまくやるんだろうな、そうであってほしいな。
歩いているときはずっと猫を探している、と言えるかもしれない。あるいは、猫をその痕跡から探している。猫の家、水や餌用の器。猫そのものを見ていなくても、猫のことを思い出す。旅に出ながら猫のことを思い出そうとしている。猫を思い出して、京都の猫のことを思い出す。古代ギリシャの遺跡を見て、京都で関わっている場所の庭を思い出す。アクロポリスでパルテノン神殿を見て、両親のことを思い出す。ギロ・ピタを見て、またしばらくギロ・ピタが食べられなくなることを思い出す。後になってテキストを書いて、それらのことをまた思い出す。
数か月間かけて、ときどき書き足していきます。
021425 自宅にて
こういう時間を過ごすのは随分と久しぶりだなと思う。それがどういう時間なのか、自分もよくわかっていない気がするのだけど、たとえばパソコンの前で着地点のわからない文章を書いている時間でもある。大切な時間なのだけど、息継ぎみたいなものだからいつもやってくるわけではない。小刻みにやってくることもあれば、なかなかやってこないこともある。でも、それがやってきたときには面倒がらずに向き合って考えたほうがいい。それができないと、回さない方がいい歯車を回し続けてしまうかもしれないから。
あと、できれば何かが終わる前にそれがやってきてほしい。何かが終わる前にたくさんのことを反省し始めたほうがいいだろうから。
最近、博士課程に入学するための試験を受けて、無事に合格した。その合否発表の日はある場所の工事初日で、それはそれはとっても大切な日だった(試験のことは二の次だった)。
工事に向けてできる限り多くの想定をして、そのおかげでとても不安になっていたのだけど、実際に建物にさわり始めるとそれらが杞憂に終わりそうな気がした。それで少しだけほっとした気持ちで初日の作業を終えた。
その夕方、お世話になっている工務店の方にインパクト・ドライバーを買ってもらった。makitaの18V、最新モデルのインパクト・ドライバー。ずっと古い12Vのインパクト・ドライバーを使っていたから、それを見かねて買ってくれたのかもしれない。他にもいろいろと工具を買ってもらって、なんだかその昔のクリスマスに野球グローブを買ってもらった日みたいだった(確かにそういう日があった気がする)。
博士課程入学試験の合格と杞憂とインパクト・ドライバー、とっても嬉しい組み合わせだった。
試験に際して読み返した修士論文には、場所に長い時間をかけて関わり続けることと空間の非暴力的な緩やかさの関係が書かれていた。長い時間をかけて場所に関わり続けることの中で、ある存在はその自己を遷移させながら、場所に異なる空間を複層していく。その複層化された空間同士の非一貫性、その多孔性に他者が存在可能な緩やかさが生まれるのだということらしい。無意志、例えば壊れていることに起点を持つこと、意思、すなわち設計をすること、そうして建築に合わせながら建築に合わせてもらうこと。
そうした緩やかさと併せて、ずっと穏やかさのイメージがある(もしかすると静謐さの方がいいかもしれない)。自分の心までそれに染まってしまうような空と水面の響き合い、震災跡地の単純化された風景、自宅の天窓からの光景。
修士論文を書いた後、自分の中ではある種対称的な関係にあるこの2つが同時に存在することをぼんやりとイメージしていて、最近やっとそれを空間にできそうな予感がしている。3月はしばらく南欧で過ごすことになっているから、その間にこれについて少し長い文章を書いてみたい。それでその後、自宅で試してみようと思ってなんだかわくわくし始めている。もちろん、そのときには買ってもらったインパクト・ドライバーも使って。
123124 Mind my/your own business@自宅
とある打ち合わせの前に、谷町で目に付いた喫茶店に入る。入口に掛けられた「当店の珈琲は芦屋の水を使用しています」という看板の示したいところが僕にはよくわからない。雀卓にフィルムシートを被せたような席について、モーニングをお願いする。隣の席で、ふんぞり返った設計者と背中が丸くなった施工者が打ち合わせをしている。「このパースで本見積。来週までに。いいクリスマスプレゼントを待ってるわ。」その場から逃げ出したい気持ちと、こんなことがまかり通っていい訳がないという気持ちが生じる。
ときどき胸が詰まるようなときにはフランク・オーシャンの「Future Free」を聴く(そうではなくても聴く)。
開きすぎた部分を意図的に閉じていって、心地良い状態をつくる。生きているといろんなところが開きすぎてしまう。ときどき自分にうまく調子を合わせないといけない。
博多から京都へ、新幹線で戻る。年が明けるといくつかの現場が動き始める。変化が生じて、それがしばし場所に固着する。時間にはたくさんの尺度がある。ただそれが数年、あるいは数十年のことであるとしても、変化というのは大きなことなのだと思う。それに、ある変化が影響を及ぼす時間尺度は、想定よりも実際の方が長くなる傾向にある。それは身の回りのことを見れば、どこからだって理解できることだと思う。
自分の思考がなんらかの空間としてかたちを持ち始めることには喜びと怖さがある。それほど大きな場所ではないのだけど、それでもこの怖さは何回やっても無くならない。そしてそれはスケールの問題ではない。それはそうと、博多はなんだか蠢いている場所で、いたるところで大規模な工事が行われている。善悪を問いたいわけではないのだけど、一体なぜそんな行為を決定できるのかを知りたいと思う。ときに、スケールは重要な問題である。
思考は、試行は、ある瞬間を境にしてかたちを持ってしまう傾向にある。でも頭の中では変化し続けていくし、それらを取り囲んでいる状況も変化する。そうした理解において、建築の可変性、仮性を問う議論は近年盛んになってきているように思う(あるいは多義性を問う議論もある)。ただ多くの場合、そこで語られる仮性は、仮とはいえ一度はかたちを持ってしまうことの重大さを軽んじているものが多いように思われてしまう。
さて、そうではないものを考えたい。循環とかサーキュラーとか分解とか、そういうある種の軽さが付きまとうものではない、長い時間への態度がある。もっと積極的に固着化させたいし、もっと積極的に仮化(多孔化)させたい。練り上げてきた自分なりの思考をかたちにするというのは喜ばしいことではあるのだけど(そのためにやっているのだから)、いつまでも練り続けていたい気持ちもある。
仕事を早めに切り上げて、小さな集まりに参加する。良い予感はなかったのだけど、想定以上に嫌な思いをして気分が下がる。でも他の人たちは楽しそうにしていて、僕もなんとなくその場の雰囲気に合わせてしまう。傷つけられていることから目を背けてしまう。
その後は家に帰ってもなかなか気持ちが切り替わらなくて、ぼんやりしてしまう。発せられた言葉の正誤の問題ではない。誤った言葉でも、十二分に相手を傷つけることができる。この年末年始の、誰からも電話がかかってこないあいだに済ませておきたいことがあったのだけど、完結的につくり上げようとした自分のペースは大外から回り込んできたものに壊される。常々のことではあるが、世界はどうしようもなく孔だらけだ。
一晩経って、開きすぎていた開口部を見つけて閉じる。気持ちをつくりなおす。開きすぎた孔から入り込んできたもののことを考えて、そして自分の誤りについて考えて、今度はうまくやれるようにする。
そうやって遠回りして、そうなるはずだった(かもしれない)12月30日にたどり着く。でも実際には今日は12月31日で、12月30日はもう帰ってこない。そして書き残したいと思うことが増える。次は間違えないために、書き残す。
それはそうと、お正月はあったほうがいい。電話が鳴らないから。
112424 @ 自宅
友人と共同で「練習/Rehearsal」という小さな展覧会を開いた。
展覧会をさせていただいたからなのか、会期後には無性に誰かの展覧会に行きたくなった。それである人に勧めてもらった下道基行さんの「ははのふた」という展覧会を訪れた。8畳ほどの小さな空間に写真が数枚と短いテキスト。とっても素敵なものだった。そこには、生きている中でなぜつくるのか、なぜつくらなければならないのか、ということが素直なかたちで存在しているように感じられて、すごく勇気づけられるものだった。僕にも少なからずそういう感覚はあるのだけど、今はまだそれを明確に示せる人に及ばない。でもとっても清々しい気分になった。良い時間だった。
数年ぶりに徳島に行って、かつて暮らしていた場所を車でぐるぐると周った。 人工埋立地の旧印刷所はスポーツを中心とした施設になっていて随分と賑わっていた。ほとんど人けがなかった場所が賑わっているのは不思議なことだった。しかし、そこにあったのは、この場所で生きていた自分としても素直に理解できる光景で、とても豊かに感じられた。ただ、そこに設計された建築には疑問があった。そこに生じていたある種の豊かさは建築の力によるものではなく、ただスポーツの力によるものだと思った。建築はただ気休めとして、その場をほどよく濁し誤魔化ために存在している。ヒロポン建築。いったいいつまで、こういったその場しのぎの劇薬的な建築行為を繰り返すんだろうか…。こういうことはほんとうに中毒的だと思う…。
海沿いの人工海浜公園からいつものように辺りを見ると、いつの間にか高速道路がどんどんと連なっていた。
小さいころ、よく行っていた鉄板焼屋でよく食べたメニューをいただく。高校生のころ、帰り道によく寄っていた何でも屋みたいなところに行く。店主の彼は様子をうかがいながら、久しぶりやなと声をかけてくれた。覚えていてくれてうれしかった。前の道路工事も進んだねと言うと、そうかあ?と言われた。確かに、毎日見てるとほとんどに進んでないのだろう。
徳島から京都に戻って、ずっと積み残していた翻訳の仕上げに取り掛かった。翻訳は楽しい。誰かが書いたこと・話したことを出来る限りそのまま受け止めて、それを尊重して吐き出す。そのあいだ、自分に他者が重なり合う。とはいえ、それは一元的な重なりではなくて、やはりそこでも他者は他者であり、それとは異なる自分というものがある。二元的な思考にとどまりながら、他者を想像する。翻訳にもそういった多孔性とアチューンメントがある。そうしてまた修士論文で書いたことに戻ってくる。そろそろ次に行きたい。
良いリズムに乗り始めたところで、当て逃げにあった。フロントバンパーの右側が割れてしまっていた。どうにかして犯人を探そうという気持ちはあまり湧かず、さっさと修理して無かったことにしてしまいたいという気持ちが勝っていく。かき乱されたままにされたくはない。そう思いながら少しだけ待っていると申し出があった。最初からそうだったのだけど、当人を前にしても怒りの感情は全くなくて、もはや感謝していた。「あなたが申し出てくれたおかげで、私は気分良く自分のペースで生きられそうです!」といった感じで。
結局、相手の保険でフロントバンパーの取替修理をすることになったのだが、そうすると、車を譲り受けたころに柱に擦ってつけた左側の傷もなくなることになる。柱に擦ったこと自体は大した思い出ではないのだが、その傷とはずいぶん長いあいだ一緒に過ごしていたから、居なくなってしまうと思うと少しさみしい。
あたりまえのように、残しておきたい傷跡がある。建物の改修を考えてると、ほんとうにそういうことに思慮が及んでいるのかと不安になる。そしてときどき、どうにもならない他性に突き動かされ、そうした傷跡は強引に消されてしまう。そういう現実をどう理解して生きていったらいいのか、まだよくわからない。
ありがたいお話をいただいて、来年度の仕事を考え始める。築50年のRC部に木造が乗っかったような住宅の改修。
家の近所でRCのマンションが解体されている。前を通ると、胸が詰まるような大きな音がしていることもある。そういう状況を前にして、想像する、あるいは 練習/Rehearsal する。こうした出来事が自分事として起こり得る。そのときに、どういう未来に向かって手を伸ばしたいのかを考えること、それはほんとうに重要な課題になりつつある。
多孔的であることについてのメモ書き
ふと思い出して気に入っていた音源を聴こうとすると非公開になっていた。連鎖的に思い出した対談を読み返そうとするとウェブページが削除されている。以来、それらを聴くことも読むこともできないでいる。家のどこかに眠っている印刷されたページは役に立たないどころか、そんなことはするべきではなかったのではないかと考える。ひょっとすると、今は見せたくないことなのかもしれないから。
小袋成彬の『分離派の夏』は依然として輝き続けているし、『Piercing』には他者に開かれていくことへの勇気をもらう。大切なのは、閉から開へのプロセスなのだと考える。きっとそのときが訪れると信じて待って、慎重に慎重に開いていく。少しずつ花を開かせるイメージ。先んじて存在するのは、というよりは思考が可能になるのは、やはり閉の方である。
とあるプロジェクトで、自分よりも少し立場が上の人(そのことは表面的には隠されている)から、それはないでしょう…というようなことをされ、これはダメだと思って反論する。だけれども、それに憤っているのは自分だけなのかと感じられて腑抜けにされそうになる。それに、ここではその悪気のなさがむしろ厄介だ。悪は実態を持って存在しないから。ともかく、油断して開き過ぎたと反省する。話し合おう。事後的になってでも、開き過ぎた無規定な孔を制御したい。直感的に、事後的な制御の方が今日的には大切かもしれないなあと思う。
大学院生の頃に、とある設計事務所でプロポーザルに参加していたときの苦悩を思い出す。そのときに感じたような理不尽からはできるだけ離れて、あるいは自分だけはそういうことをしないように生きていこうと思ったのだけど、結局そういうことは至るところにあって、気が付いたときには巻き込まれている。それで、自分もまたそういう存在になってしまう、あるいは既になっているのではないかと思って自分の行動を思い返す。そうして、これは気遣いや配慮といった問題であることを再確認する。
重層下請構造。ほんとうに問題なのはコストなどではなく尊厳である。
「多孔的である」ということをずっと考えているのだけど、やはりそこには何かを制御しようとする意志がベースにある。制御しながら、何かに(誰かに)部分的に開いていく。慎重に、疑いを持って。
多孔的であり得たと思える出来事から原広司の『建築に何が可能か』を再読して、そこに綴られた言葉に再び勇気をもらう。ちょうど1年前にも同じようなことをしていたと思う。
街中で猫を見かけるとなんだか安心する。足を止め、しゃがんで、話しかけてみたいと思う。反応が無くても全く気にならない。少しのあいだ、猫の調子に自分を合わせてみたいと思っているだけなのだろう。あまり乱れないように思われる猫の調子に。
リードを繋がれてご満悦な犬を見ていると不安になる。あの犬たちはリードを外されたときにはどうなってしまうんだろうか。頼むから、その場で立ちすくんだりしないでほしい。
釜山より──溝/gapを歩く
歩くことは、もうずっと大切なことだ。特にこの数年はそのことに意識的になっていて、去年からときどき書いている(金沢にて)。その頃から考えていたこと、歩くことをとおして身の回りのものと調子を合わせていくこと──アチューメントしていくこと──とはつまり、身の回りのまだわからない何かのこと、そのわからなさの溝/gapを想像し、それを感じ続けることでもあるのだと思う。ただ、その溝/gapを埋めようとすることが大切であるとは限らないとも感じる。溝を埋めることに勤しむよりも、溝があってもなお共にあるという緩やかさの方が大切だと思うから。歩き続けること、あるいは想像し続けることによって。
パク・ソルメという作家が『未来散歩練習』という素晴らしい本を書いていて、2023年に日本語に翻訳された。この小説らしきテキストには、韓国の釜山や光州、あるいは日本のいくつかの都市がその舞台として登場する。なかでも、釜山の「旧アメリカ文化院」(もともとは東洋拓殖株式会社の社屋として建築され、現在は釜山近現代歴史館 別館となっている)と「釜山アメリカ文化院放火事件」が物語の中心にある。これは実在する建物と、そこで実際に起こった事件である。2024年の夏、この素晴らしい本からとても大きな影響を受けた。そのことは別の機会にじっくり書くこととして、本文の中からとりわけ印象的な部分と、訳者である斎藤真理子による推薦文の一部を引用させていただく。
“チェ・ミンファンの言うように気候が変化し、動物たちが消え、地球の終わりが近づくとき、私はその窓の向こうのことを思い出し、私の欲しかった未来がもう戻ってこない美しい過去に思えるのだろうが、そのときは辛いだろうか、後悔するだろうか、または……でもそれは同時に、切実に蘇らせたい、作り出したい未来でもあった。過去の人たちが持ってこようとして努力した未来はまだ未来と感じられるし、私が思い描く未来も、未来にはまた、蘇らせたい未来となるのだろう。来てほしい未来を思い描き、手を触れるためには、どんな時間を反復するべきなのか。私はまずそれをどこかに書きとめておこうと思った。”
“現在と未来について考える人たち 来るべきものについて絶えず考え、現在にあってそれを飽きずに探し求める人々は、すでに未来を生きていると思った。絶えず時間を注視し、来るべきものに没頭し、人々の顔から何かを読み取ろうとする人々は、来るべきと信じるそのことを、練習を通してもう生きているのだと。ある時間たちは近づき、混じり合い、膨張してそこにあり、未来とは必ずしも次に起きることではないですし、過去とは必ずしも過ぎ去った時間ではないんです。”
“現在とは、単純な「今」ではなく、過去と未来の間で誰かが粘り強く続けている「練習」の時間なのかもしれない。パク・ソルメの想像力がそれを可視化する。この作家は、断言せず、逡巡し、言葉を選びながら、事実と現実と真実のあいだを慎重に行き来する。この三つの「実」のどれもこぼさずに過去から未来へ運ぶことはとても難しい。だが、パク・ソルメはそれを勇敢に、そして何気なくやりとげる。散歩するために出てきたような身軽な様子で。”
以前から、船で釜山に行きたいと考えていた。下関から夜行船に乗って釜山に行くことを想像する。大きな船に乗って日本という島の外に出ることは、とても魅力的な経験に思えた。そしてそれが実際のこととなるようにイメージして、いくつか具体的な行動をする。旅程を調整し、見知らぬ街についての事前情報を少しだけ取り入れ、船酔いについて対策を考える(ありがたいことに杞憂に終わった)。果たして、それは現実になる。
sanpo 1
朝になって船室で目覚めると、船はすでに釜山の港に停泊しているようだった。甲板に出ると、港の向こう側には馴染みのない佇まいの都市が広がっている。山肌をトレースするように細々と建て続けていたものの、ついにどうにもならなくなった、という具合に山よりも山らしい高層ビル群が建てられていた。
下船して、港から釜山駅へとつながるペデストリアンデッキを歩いていると、さまざまなものが目に入ってくる。2030年万博の誘致広告(開催地はリヤドに決まっている)、それに合わせるように開発される予定であった巨大な埋立地(開発は継続するようだった)、山を隠す壁のような駅前の高層ビル、高層ビル、高層ビル、大規模な道路工事。含みなく、ただ目に入ってきた事実を書きあらわしたい。
1950年代、朝鮮戦争時の疎開による急激な人口増加を経験したのちに、現在は急激な人口減少期にある釜山。この巨大な試みたちに、どれほどの素晴らしい、「来たるべき」未来が含まれているのか。なぜこれは実行されなければならないのか。もちろん僕にはそれはわからないのだけど、これを実行しようとしている人々だって、実のところはわかってないんじゃないかと想像する。そうだとすれば、いったい何がこれを推し進めようとしているのか。旅の始まりから息が詰まるようで、少し辟易しながら、隠されつつある山に建つホテルへと歩いていく。
ホテルに荷物を預けてから斜面を下り、海沿いの市場を散見する。海産物、野菜、飲食店、偽物らしきブランド品、可愛らしい照明器具、調理器具。そうして色んなものを見ているとお腹が空いてきて、街角でキンパを買って食べた。これがとっても美味しかった。
それでいつの間にか近くまで来ていることがわかって、「釜山近現代歴史館 別館」へと向かった。「釜山近現代歴史館 別館」の建物は1929年に東洋拓殖株式会社の釜山支店として建築されたものである。解放後は米軍の宿舎として利用されたのちに、アメリカ文化院に利用されていたのだが、1999年になって韓国へと返還されたらしい。そして何度かの改修を経て、2023年からは図書館を中心とした文化複合施設となっている。
パク・ソルメの『未来散歩練習』に導かれながら見知らぬ場所を歩きはじめる。こういうことはとっても楽しい。それに、旅先でホテル以外に落ち着いて作業ができる場所を見つけておくのはとても大切なことだと思う。
歴史館で少しゆっくりとしたあとは旧百済病院を訪れた。この場所は1922年に釜山初の近代総合病院として開院し、1932年の廃院後は中華料理店、日本軍将校の宿舎、釜山治安司令部などとして利用されたらしく、現在はカフェや書店、ギャラリーなどの複合施設となっている。1階のカフェはとても人気なようで、この日も多くの人で賑わっていた。せっかくなので、われわれもそのカフェでコーヒーを飲みながら少し休むことにした。どうやら韓国ではアメリカーノが主流らしくて、街角のコーヒー・ショップではたいてい安くて大容量である(このあとの散歩では、その大部分でアメリカーノを片手にしていた。薄味だから歩きながら飲むのにぴったりだった)。
建物を一通り見て回った後、入り口付近に少しだけ建物の過去に関する展示がなされていることに気が付いた。100年を超えて、その姿を変えながら釜山の近現代と共にあり続けてきた建築。その時間の中に、いったいどのようなことがあったのだろうか。なぜこの建物は残ったのだろうか。そしてこれからも残り続けるのだろうか。残ってさえいればいいんだろうか。
同時に、今に残らなかった建物のことを想像する。建物はなぜ、時に捨てられたり壊されたりするのだろうか。もっともらしい理由はそれなりに思いつくのだけど、決定的に重要なことが見落とされているような気がしてならない。
これらのことは、いつの間にか会期が近づいている展覧会のようなもの(京都のとあるビルの100周年に関連するもの)に関わることでありながら、今取り組んでいるいくつかの住宅のプロジェクトに関わることでもあって、なんだかこの半年ぐらいはずっとこういうことばかり──時間のことばかり──考えているなあと思う。
夕方になって少し涼しくなったころ、釜山の中心部である南浦洞から大きな橋を渡って影島へと歩いていった。とある雑誌で見つけた海沿いの書店に行きたいと思った。今日はもう十分すぎるほど歩いていたのだけど、まだ歩きたいと思っていた。朝に比べると空はずいぶんとすっきりした様子になっていて、歩きたいという気持ちはそういうことにも後押しされていた。
しかし、いくつかの坂を超えて1時間ほど歩いてたどり着いたその書店は、少し前に閉店したようだった。とても残念だったのだけど、そこに行きたいという気持ちに導かれてずいぶんと長く歩いて来られたことは満足な出来事だった。それで少しだけ夕日を眺めてから南浦洞の方へと戻った。
そうしているとすっかりお腹が空いた。それで『未来散歩練習』にも出てくる「石器時代」まで歩いて、五香醤肉と焼き餃子を食べながらビールを飲んだ。焼き餃子は僕には揚げているように思えたのだけど、やはり焼き餃子らしい。たしかに、そういうこともあるだろう。ここでは揚げは焼きに包摂されるのかもしれないし、揚げなんてないのかもしれない。もしかしたら、揚げこそが本質的には焼きかもしれない(それっていったいどういうことだろう)。
さて、「石器時代」はずいぶんと繁盛しているお店で、店先で少しだけ席が空くのを待ったのだけど、そのときからお店の若い男性がずいぶんと良くしてくれた。彼はかなり大柄で、優しい目をしていた。言葉が通じないときにこそ、自分が見知らぬ相手のどこを注視しているのかに自覚的になる。それはそうと、とっても美味しい料理にすっかり満足して、その日はもう少しだけ歩いた。
sanpo2
翌朝、ホテルから坂道を下って釜山近現代歴史館の付近を歩く。同じ場所を繰り返し歩くことは旅先で大切にしていることだ。小さなルーティンをつくる。明確な理由はないのだけど、そうした方がいいということは経験的にわかっている。
この日は釜山ビエンナーレの会場となっている釜山現代美術館に行った。去年からお世話になっているアーティストが参加していることもあって、釜山ビエンナーレを見に行くことは旅の具体的な目的の1つだった。ビエンナーレのテーマは<Seeing in the Dark>であった。釜山行きに際してさまざまに情報をくださった先生によると、このテーマはフレッド・モーテン(Fred Moten)の思想に影響を受けているらしい。さて、ビエンナーレにはいくつかの印象的な展示があったのだけど、Hong Jin-hwon による映像と写真の展示が特に興味深かった。
美術館でゆっくりと過ごして、それからはヘロヘロになりながら街中に戻ってロッテリアでハンバーガーを食べた。夜になって釜山の中心部で一番大きいらしい本屋に行くが、探していた本は見つからず、仕方がないので帰国してからAmazonで買おうかと考え始める。
sanpo3
翌朝も同じように、ホテルから少しだけ違う道順で坂道を下って釜山近現代歴史館のあたりに行く。この日はそこでしばらく作業をするつもりだったのだけど休館日だった。仕方がないので近くのスターバックスに入った。とても寒かった。
お昼ご飯にデジクッパを食べてから、南浦洞にある釜山デパートに行った。地下は食堂街、1階と2階がテナントスペースになっていて、3階以上は事務所や住居となっているらしい。建物の中に入ってみると、なんだか人けがない。それで少し様子をうかがいながら1階を歩き回って、それから2階に上がる。両階ともに、細い廊下の両脇に、効率的に工芸品や骨董品、あるいは高麗人参を売るテナントなどが配置されている。そしてその空間性とは裏腹に、テナントが欠けているところも見受けられる。
そうして歩いていると、2階の階段室の脇にとても魅力的な焼き物が並べられていることに気が付いた。手に取って見てみたいと思って、お店の人を探したけれど、この場には居ないようだった。それでどうしようかと考えていると、隣のお店のおばさんが「壁に書かれた番号に電話しなさい」と身振り手振りで伝えてくれた。伝えられたとおりにすると、日本語を話す男性が電話に出た。彼はお店の店主らしく、電話であれこれとやり取りしているうちに、15分ほどで釜山デパートに行くことができるから待っていてほしいということになった。
その時間通りにやってきた彼は70歳前後の韓国人だった。さっきは日本の番号からの着信だったため、日本語で話し始めてくれたらしい。それで、われわれが興味を持った焼き物のことをあれこれ教えてくれた。そして小さめの赤い壺を買うことにした。彼はどうもおしゃべりが好きなようで、近くの地下街にある彼の別のお店に連れて行ってくれて、そこでお茶をたててくれた。日本で働いていた経験も長いらしく(彼は流暢な日本語をとてもゆっくりと話した)、当時のことをさまざまに話してくれた。そうしてひとしきり話をしてから釜山デパートに戻って赤い壺を受け取った。彼は釜山デパートのことを案内してくれながら、何度も「ここはもう死んだから」と言っていた。ゆっくりとした丁寧な口調から繰り返される「もう死んだから」という言葉は、正負の感情から離れた聞き馴染みのない雰囲気を持っていて、とても印象的なものだった。
そのあとは大きな道路を挟んで向かいに建つロッテデパートに行き、そこが提供する無料のコインロッカーに荷物を預けた。釜山デパートの効率的で機械的な空間性とは異なって、ロッテデパートは巨大な曲線の吹抜け沿いに大きな通路が確保されていて、吹抜けでは噴水ショーが行われている。ずいぶんと享楽的な空間だと思った。建てられた時代や資金力が違うのだからと言われれば、両者の違いにも一定の納得感があるのだけど、建築することへの決定的な感覚の違いが存在していることもまた大切な事実なのだと思う。くどいようだけども、これはどちらが良いとか悪いとかそういう話をしたいのではなくて、ただそこに決定的な溝/gapがあるのだという話である。
その日はそれから西へ西へ、釜山有数の観光名所である甘川文化村の近くにある碑石文化村へと歩いていった。道中はとにかく急な坂道を登っていった。途中のヘアピンカーブごとに、その縁に年配の方々の集まりが開かれている。彼らはこっちを見て物珍しそうにしていた。それで少しだけ笑顔を送る。こちらは怪しいものではないつもりです、といった具合に。そうすると少しだけ笑みを返してくれた。
1時間ほど歩いてかなり高いところまできたなというところで碑石文化村にたどり着いた。ここは朝鮮戦争時、疎開による急激な人口増加のため居住地を確保できない状況のなかで、日本人の共同墓地の上に建てられた集落である。現在はその歴史を示す文化村として観光資源化されているとともに、引き続きそこに住まう人たちがいる。
墓石を建材として利用するなどの切実な建築行為とは裏腹に、この場所でも建築は少しずつ放擲されつつある。建築当時の想いと現在の状況があまりにも合致しない。ここにもまた溝/gapがある。ふと歩いてきた道──かつて誰かが戦火を免れて歩いてきた道──を振り返る。果てしなく続くような人工物の海の中で、ずっと向こうのほうにまで高層マンション群が連なっている。それらは一定の地面を確保したのちには容易に巨大な内部空間をつくりあげているようだった。その容易さと、この碑石文化村の困難さのあいだにもまた大きな溝がある。各時代の技術力の違いだということもあるのだけれど、それだけでは解釈しきれない何かがある。
釜山という場所ひとつをとっても、都市の部分同士があまりにも嚙み合わない関係にある。われわれはそのような溝/gapの中を生きている。ふと、5月に開いた研究会で富樫遼太さんがおっしゃっていた「不整合」という言葉を思い出す。
そして、碑石文化村から少しだけ先のことを想像してみる。あの高層マンション群はそのいつか、いったいどうなってしまうのだろうか。切実につくられた建築たちも、あらゆる理由において捨てられていく。それらをつくった、あるいはこれからもつくろうとしている人間たちの、いったい誰がそのことから目を背けずに考え、想像し、来るべきときのために「練習」をしているのだろうか。
たとえば、高層マンションはその数本のエレベーターによって、この斜面地の建築が経験しているような地理的困難をほんとうに乗り越えられるのだろうか。そういった考えはどうにも脆いものだと感じる。そして、そのエレベーターをつくる技術、あるいはそれがつくられることを認めることは、かつて切実な想いでつくられたこの碑石文化村が放擲されることと無関係ではないはずだった。さて、われわれはいったいどこに向かっているのだろうか…。
釜山に降り立ったときから抱いていたぼんやりとした違和感が、碑石文化村を歩くことで少しずつ具体的な考えになり始めていた。
夜になってサムギョプサルを食べにいく。さっきまで碑石文化村から見ていたひときわ目立つ高層マンションの麓を歩いて過ぎていく。下調べしておいてくれたお店のサムギョプサルはとても美味しくって、お店を営むおばさんたちはとても優しく接してくれた。それですっかり心地の良い気持ちになって、また坂道を登って帰る。
ホテルの部屋で今日手に入れた壺を眺めていると、この日のさまざまな感覚がそこに紐づけられることに気が付く。この壺はそんなことを想像したことがあったのだろうか。でもそういったことによって、この壺はわれわれにとってより大切な、入替不可能な存在になっていく。
sanpo4
今日も坂道を下って釜山近現代歴史館のあたりへと歩いていった。何も期待せずに繰り返し繰り返し同じところを歩いて、そうしていると意識の外側から、思いもよらない何かが得られるかもしれないと想像する。そして今日は歴史館の中でゆっくりと過ごした。2階の小綺麗な作業スペースが妙に印象的なものに思えた。
そのあとは昼ご飯に美味しい石焼ビビンバを食べて、まだ見ていなかった釜山ビエンナーレの展示会場を見て回った。それから少し親しみが生まれた釜山デパートの地下にある食堂街にも行ってみた。お昼時を過ぎたころでお客さんはほとんどいなかった。普段からいるのかもわからない。でも、きっとそれなりにお客さんがいるんだろうというような大量の食器を黙々と洗っているおばちゃんたちがいた。
昨日のおじさんはしきりに釜山デパートのことを「もう死んだから」と言っていたけれど、建物や場所が死ぬというのはどういうことなんだろうか。あるいは、それらが生きているというのはどういうことなんだろうか。ともかく、死んでいるから悪いとか生きているから良いとか、そういう基準で物事を見て、何かを考えたいわけではない。
夕方になって、日本に帰る船に乗り込む前にロッテデパートで夕食とお土産を買った。ロッテデパートは生きているという部類に入ると思うのだけれど(釜山デパートと比べると尚更そういう表現にならざるを得ない)、ときどき息が詰まるような場所だった。日本でもこの種の感覚になることは多い。過剰で落ち着きのない、動きすぎている場所が多い。とはいえ、とうぜんなのだけど、ノスタルジーを求めたり、都市性を忌避したりしているのではない。ただその場所が、歩き続けていても疲れるばかりでどうも調子が合っていかないというだけのことである。
ロッテデパートからはタクシーに乗って港へ向かった。出国の手続きもあっという間に済んで船に乗り込む。行きは日本船だったけど、帰りは韓国船に乗ることになった。韓国船のホールは華やかで豪勢なつくりがとっても魅力的だった。でも船酔いすると良くないと思って船室でのんびりと過ごすことにした。
081624 @Cafe Collection
今年のお盆も京都で過ごしている。
自分にとっては、お盆といえば徳島の阿波踊りということになるのだけど、今年もついに行くことができなかった。でも、行くことができなかったというと少し語弊があって、阿波踊りに行くこともできたのだけど、京都に残ることを選んだのだった。それでも、ちょっとした後悔が残っている。
前回行こうとしたときには体調を崩してしまい、その前に行こうとしたときにはちょうど台風がやってきてしまった(それでも一部の人たちは踊っていたようだが…)。これからも阿波踊りが開催され続けるかどうかは、ほんとうのところはわからないことであり、自分がそれに行くことができるかもまた、わからないことである。そう思うと、なんだかとても勿体ないことをしたんじゃないかと思って少し悲しくなる。
その代わりに、というとおかしな話なのだけど、大学に入って以来ずっとお世話になっている恩人が初めて阿波踊りに行くというので、あれこれとおすすめしておいた。阿波踊りを見るための場所や近くの真っ赤なラーメンショップのこと。阿波踊りについて、誰かになにかをおすすめするというのは案外はじめての経験だった。とっても嬉しいことだった。
それはそうと、阿波踊りはとっても良い。あらためてそう思う。
街中がなんだか浮ついていて、そういった場の高揚感と、踊りや鳴り物のリズムが響き合い、高まっていく感じがある。踊りはいたるところで繰り広げられるのだけど、僕は繁華街の小さな円形の交差点で見るのが好きだった。そこには、とにかく大きい音を出したいといった具合で反り返ってお腹の太鼓を叩く強面の大男や、なんだか毎年、内輪の流行を取り入れたようにバク転をしたり、糸で操られたように踊ったりする運動神経抜群の踊り手がいて、大勢の観客が団扇で暑さを逃がしながらそれを取り囲んでいる(踊りに使うこともあって、その期間は団扇が街中で配られている)。
少しずつ加速し、大きくなっていく鳴り物のリズムや、左右に揺れる団扇のリズムが自分に浸透してくる。それでだんだんと、逸るような熱い気持ちが内側からも湧いてきて、場と自分の輪郭が曖昧になっていく。ある種の共振状態となっていく。阿波踊りというと、その情景が頭に浮かぶ。
なにより、予定調和的なショーとしてのお祭りとは異なる、その場で刹那的に生まれた空気感、祝祭的な微熱感が確かにある。演者と観客は、ある意味では不可分に、同じ温度の中に包まれている。祭りにおいてそういったことは本来的なのだろうけど、あんがい(今日においては)そういうお祭りは少ないように思う。
お盆の前には数日かけて長野県と愛知県を訪れた。
ある住宅のプロジェクトに関連した目的地を何か所か回って、いくつかの物と気付きを持ち帰った。いろいろと想定はあったのだけど、それとは異なる感覚をその場で得た。じっさいに動くことの良さは、そういうところにある。
気が向いたときに、そのプロジェクトについての少し長いテキストを書き続けているのだけど、またそれを編集する必要が生じる。そうやって実際の経験に導かれて、絶えず感覚は変容していく。
最近いくつか面白い本を読んで、今もいくつか面白い本を読んでいる。
本屋でなんとなく読もうと思った本や誰かにおすすめされた本など色々とあるのだけど、そのどれもが、どこか未来について考えている本だと感じた。それも、過去・現在・未来をある意味で同時に捉えようとするものだった。直接的にそういうことを書いているものもあれば、こちらがそう解釈しているであろうものもある。
とはいえ、ひょっとすると、未来について書いていないテクストの方がめずらしいのかもしれない。あるいは、今日においてはそういった潮流のようなものがあるのかもしれない。はたまた、未来──過去や現在と不可分なものとしての未来──を考えたいと思っているから、あらゆるテクストがそう解釈されるのかもしれない。
ともかく、最近はよく、実感を補填するような新鮮な気付きがあって嬉しい。こういう感覚はなんだか久しぶりだなあと思う。
その間に、長いあいだ積み残しになっていた仕事が少しずつ整理されて行って、ちょっとずつ新しいことに移行できている。それもまた、とっても嬉しいことだ。
さて近所では、もう少しで山に火をつけるイベントが始まるらしい。せっかくだから、このカフェから家に帰る途中に、少しだけ振り返ってその様子を見ようかなと思う。でも、この場所からいっさい後ろを振り返らずに家まで帰ったとしたら、それを目にすることはない。
多くのそれを見つめる人たちを脇目に、それとは無関係にこの場所に潜伏しているように通り過ぎる、そういうのも悪くはなさそうだとは思うが、たぶん振り返るだろう。
福岡より
福岡へ──のぞみ1号 博多行
新しい仕事のために、福岡に向かっている。
とある縁から、福岡で設計の仕事をさせていただくことになった。その敷地にはいくつかの候補があって、それを決定するために、そして関係者の方々と顔を合わせるために、福岡に向かった。
朝の7時半、京都の自宅を出て、バスで京都駅に向かう。この時間帯にバスを使うことはほとんどない(他の時間帯でもめったに使わないが…)。車内はすでに観光客らしき人々でそれなりに混雑していた。
30分ほど経って京都駅に着いたバスの車内には、乗車に関するあれやこれやを理解できなかったと思われるたくさんの外国人観光客と、その対応に辟易として、つい言葉が荒くなる運転手がいる。運転手の彼は、その観光客たちに向かって妙に早口の英語を話しているのだけど、それは苛立ちを込めた日本語のように聞こえる。 "Where did you get on?"
気を持ち直して、中央改札口の近くで切符を買い、博多行きの新幹線に乗り込む。のぞみ1号 博多行。2年前、車で九州を一周したときには滞在しなかった福岡。それはいつか仕事で来るだろうという予想に基づいた判断だったのだけど、あんがい早く現実となった。
そう、普段は遠方にも車で移動することが多い。そのためか、京都から博多までの移動時間が2時間半だということに違和感がある。とても短い。でもこれは仕事だから、急いで移動しなくてはいけない。だから新幹線で行くべきだ、と考える。そういう思考のあり方が自分の中にも存在していることがわかってしまう。
どれだけそうしないようにと思っても、仕事/それ以外という構図が無意識に浮かび上がってくる。そしてときに、仕事であるという意識は人に「何か・誰か」の思考を無自覚に入り込ませてしまう。われわれ──孔だらけの存在──は、それを制御しなければならないはずだった。自身を入替可能な存在へと落ちぶれされる思考が入り込むことを。
少し前に、濱口竜介監督の『悪は存在しない』を見た。とても良い映画だった。悪は実体を持って存在しない。空っぽで孔だらけの存在者たちが、一時的にその悪のウツワとなってしまう。流動的で掴みどころのない悪。
遠く離れた場所で設計するということへの漠然とした怖さがある。それでも、自分が大切に思うことに自覚的になって、できる限りの誠実さで関わることが大切なのだと思う。そうして、具体的なひとつひとつと関係を結んでいく。
そんなところで、抽象的な思考を手放す。
スマートフォンを使って、いつものパスタをつくるうえでの具体的な注意点をメッセージする。こちらはただいま東広島、外には青々とした緑と石州瓦による赤の風景が広がっている。でもぼんやりとしている間に過ぎ去っていった。いや、こっちが過ぎ去っていった。
平尾にて──いくつかの可能性と方向づけとしての選択──
京都へ──のぞみ20号 東京行
翌朝、天神の宿を出て、朝ご飯を探しながら博多駅方面へと歩く。10分ほど歩いたところで素敵な佇まいの喫茶店に出会い、そこで朝カレーとホットコーヒーをいただいた。カレーは深みのある辛口で、コーヒーはそれに見合う濃い味わいだった。とても美味しかった。きっとこれがベストな関係性なのだと、絶対的にわからせてくれる。ちょうどカレーを食べ終わるころにコーヒーを出していただき、そのタイミングも完璧だった。
すばらしくアチューンメントされた全体、それでいて過剰さを伴わない何か、それを感じてとっても良い気分になった。
そこで一息ついてから、博多駅に移動して新幹線に乗り込む。のぞみ20号 東京行。今日のところはできるだけ早く京都に戻りたいと思っていた。
新幹線の座席で、パソコンを開く。福岡で過ごすあいだ、その裏側で──京都で──いろんなことが蠢きはじめていた。メールのプッシュ通知がそれをほのめかしていた。そのほとんどが、とっても前向きなことなのだけど、ほんとうにそこに入り込むためには、たくさんのエネルギーが必要になる。
今大切なことは、ひとまず頭じゃなくて手を動かすこと。とにかく、つくること、書くこと。まずはこの新幹線から再開する。そうして、少しずつ自分自身を別の状態に遷移させていく。
Sigur Rós - All Alright (Inni live performance)
近頃は『Með suð í eyrum við spilum endalaust』を繰り返し繰り返し聞いています。
近頃のこと──川湯温泉、大阪、尾道、ときどき京都
川湯温泉へ──曲がった道、入替不可能な何かへ
ひょんなことから、紀伊半島の中央部、川湯温泉へ行った。京都からトヨタのウィッシュに乗って、南へ約3時間。なにか大きな攪拌(disturbance)が起こったような場所を通り抜けて、進んでいく。
川湯温泉は当初からの目的地というわけではなかった。というのも、熊野古道に行こうと思っていて、それでなんとなく近くにある川湯温泉に泊まろうと考えていたのだ (ただ、選んだ宿は尊敬する先輩のおすすめであったから、とても楽しみにしていた)。しかし、じっさいには熊野古道に行くことはなく、ずっと川湯温泉にいた。それで結果的に、「このたびは川湯温泉に行ってまいりました」ということになるのだ。
さて、川湯温泉は紀伊半島の山間部、大塔川沿いの道(静川請川線というらしい)に宿が立ち並ぶ小さな温泉地で、ちょうどいい不自由さの中にあった。行動の選択肢を少なくして、のんびりと過ごすにぴったりの場所だった。
宿が立ち並ぶ川沿いの道は、川の蛇行に合わせて緩やかにカーブしていて、とにかく歩いていて心地がいい道だった。川の蛇行、途方もない時間をかけてつくられたその大きなリズムに、ずいぶんと小さな人間の、ちまちまと歩くリズムが響き合っていって、心が満たされていく。去年、ヨーロッパを旅するあいだに、いくつか印象的な曲がった道に出会って──ギリシャのクレタ島ChaniaやドイツのMechrnichで──それ以来、自分が曲がった道に魅力を感じていることに自覚的になった。それはそうと、川湯温泉の曲がった道は本当に素晴らしくって、そのおかげで熊野古道には行くことも無くなり、それでいてとっても素敵な時間を過ごすことができた(曲がった道については、また別の機会に書こうと思う)。
宿泊した民宿も素敵なところで、「古いが十分に手入れした建物」という宿側の自己評価に間違いはなかった。それに、素朴で豪華なごはんがとっても美味しかった。温泉はとても暑くてヘロヘロになったのだけど、その分、ビールが信じられないほど美味しく感じられた。いつの間にか、夏の気配がもうすぐそこまでやって来ていた。
ひとしきりのんびりと過ごして、京都へ戻ろうとする。帰路は東に、ひとまず熊野に出ることにする。
disturbance / message from a professor
熊野でお昼ごはんを食べようとしていたころ、とある大学の先生から連絡が来て、あれこれと仕事のお誘いをしてもらう。とってもありがたいのだけど、旅先での気持ちと嚙み合わず、妙な緊張感がある。億劫にならないうちに、プロジェクトを共同している彼と話を合わせて返事をする。京都に戻ったら、晩ごはんを食べながら話をすることになる。
昼過ぎに熊野を出てからは、伊賀を通るルートを選んだ。
それで夕方ごろに伊賀に着いて、とある窯元でとっても素敵な緑色の平皿をいただいた。たくさんの陶器が雑然と置かれた部屋の中で、そのお皿は明らかに一番魅力的だった。数多くの選択肢の中から、そういった光るものを選び出せたときには、そのときに感じた──感じさせられた──輝きの感覚がずっと残り続けるものだ。
そういうことは、買い物に限らず、より一般的な範囲で起こりうることである。人との出会いにおいても、建築の設計においても。こういうことを繰り返して、あるいはそのためにじっくりと時間をかけて、入替不可能な何かを手にしたい、つくりあげていきたいと思う。
入替不可能であること (正確には、入替可能ではないこと、かもしれない) は、5,6年前に宮台真司の議論に影響を受けて以来、ずっと意識していることなのだけど、近頃、重要なテーマとして再浮上している。それも建築、とりわけ (今設計している) 住宅、それをつくりあげていくプロセスにまつわるものとして。
もう少し一般的だったことが、おのずと建築に関わる領域に引き寄せられると、妙にワクワクする感じがある。とはいえ、この話は長くなるので、また機会にじっくりと書いて、いろんなことを少しずつ公開していきたいと思う。
入替不可能な長い家について。あるいは、私たちの家はすでに建ちはじめている。
今年はツバメの巣がよく目につく。
大阪へ──disturbance / meeting with the old friend
もう知り合って9年になる友人と、数年ぶりに会うことになった。
最後に会ったのは3年前、彼が東京にいたころだった。そのころ僕は東京にある恩師の事務所に出入りしていて、その間、友人宅を転々としていたのだけど、そのなかで彼の家にも1度だけ泊めてもらった。当時はずいぶんバタバタとしていて、夜中に事務所を引き上げて彼の家にお邪魔し、ほとんど話す時間もなく眠って、朝早くに出て行ったように思う。それからずいぶんと時間が経った。彼はこの春に転職し、今は大阪に住んでいるらしい。その旨の連絡をもらって、大阪で会うことになった。同時に、ずいぶんと久しぶりに大阪に行くことになった。
さて、長い期間を空けてから友人と会うことは、とても緊張することだ。
お互いの生きる環境が変わって──彼とは大学の学科こそ同じだったが、もともと環境は大きく違ったように思う──、それぞれがそこで過ごしてきた時間と変化を知ることになる。そのプロセスのなかで、自分が相対的に位置付けられ、自分がいったいどれだけ遠いところに来てしまったのか、それを思い知らされることになる。そしてときには、もう戻れない世界が──もはやその入口の見つからなくなった並行世界が──ほんとうに自分からは離れてしまったことを思い知る。
(他者と久しぶりに会うことに伴う諸々については、平野啓一郎『私とは何か――「個人」から「分人」へ 』での分人主義に関する議論の導入部がその理解をわかりやすく助けてくれる)
またしても、これは悲しい話ではない。
彼が予約してくれたお店の個室で焼き肉を食べながら、これまでのことを話し合って、お互いの違いを認識していく(そういえば、彼と会うときはいつも焼き肉を食べている気がする)。そのなかで大切に思われたのは、それでもなお、友人であることにおいて、適切な正直さをともなって話そうとすることだった。押し付けずに、それでいて押し付けられずに、長い時間をかけてお互いの調子を合わせてくこと。多孔性と制御の感覚はここでも役に立つ。そして、完全に重なり合うような合意を目指さないこと。一緒になることではなく、ただ一緒にいようとすること。
少し以前の関心に引き戻して考えてみる。
平野啓一郎は『本心』で、分人主義的な世界認識の先で「最愛の人の他者性」を問題化した。どれだけ長い時間をともにしても──あるいは長い時間をともにするがゆえに──最愛の人が他者であるという事実からは逃れられない。まあ、彼が最愛の人であるかどうかは置いておいて、平野が『本心』で示した他者の他者性と向き合う誠実さというのは、20代の後半に差し掛かって、それぞれの人生が大きく逸れ合っていく自分とその周囲の人との関係において、あらためて重要なことになっている。身近な人であるほど、長く時間をともにするほど、難しくなることというのがある。それでも、なんとか自覚的になって、できる限り誠実でありたいと思う。
そういえば、『本心』は映画化するそうです。監督は石井裕也さんで、主演は池松壮亮さん。かねてから、池松壮亮さんは代えがたい魅力を持った素敵な俳優だと感じています。そういう人ってそう多くはいないんだけど…。
彼と別れてから、梅田の喫茶店に入って会話の内容を反芻する。自分なりに書き起こして保存する。そして、梅雨が明けたころに会話を再開する。楽しみなことが増えた。
京都にて
ときどき、京都を離れてどこかに行く。そこではあたりまえだけど、良いことと悪いことのどちらもが起こって、それによって少し自分が攪拌される。その後に、少しの気付きとともに京都に戻ってきて、それまでの長い時間をかけてつくりあげてきたルーティン、その繭の中で、親しみのあるリズムに再び調子を合わせていく。
自宅のキッチンで、時間をかけてオリーブオイルに、にんにく・ベーコンの香りをうつす。そのルーティンの具体的な部分――たとえば、火や食材の様子――に注意深くなって、じっくりと、美味しいと感じられるパスタをつくる。そうしていると、脇にある建具の隙間から、隣地での変化が入ってこようとしていることに気がつく。そしてそれを受け入れようとする。今年も紫陽花が咲いている。天窓に入ってきては出ていく雲を眺めて、いつもの猫たちに会いに行く。悲しいことに、いつの間にか会えなくなった猫がいて、一方で、最近になってよく会うようになった猫がいる。先日連絡をくれた大学の先生たちと少し緊張感のある食事兼打合せをし、翌日には気心知れた友人たちとプロジェクトの打ち上げと題して川辺でピクニックをし、素敵な居酒屋でのんびりと過ごす。
安定したルーティンの中で、とにかく具体的なことに注意深くなろうとする。そうして、変化を選択的に受容する。
ときどき、そのルーティンの中に、新しい入口と出口が生じていることに気がつく。
京都留学の終わりが近づいてきた友人と会って、タイ料理を食べる。もう4年ほど定期的に会っている。多くのことを話したし、多くの大切なことを教えてもらった。ずっとここに居てほしいように思うけれど、彼には戻るべきホームタウンがあって、仕事とポストが待っている。彼は、僕がタイに行けるよう準備してくれるという。それで、たまに一緒に仕事をしようと言ってくれる。そんなことができたら、とっても幸せなことなのだろうと思う。
あるいは、またひとり、友人を京都から送り出す。同じ研究室で過ごして、その後、共同で仕事をすることをとおして、多くの感覚と言語を共有したように思う。けっしてひとりではたどり着けなかった現状に感謝して、そしてわれわれの素晴らしい未来を願って、いつもの素敵な居酒屋で晩餐をともにする。
あるいは、つくったことがないご飯をつくる、つくってもらう。苦手だと思っていたタイカレーを自分が美味しいと感じることに気がつく。タイカレーにビールという新しい夏の風物詩が自分の世界に入ってくる。
なんだかふと、人の多いところに行きたくなって、休日の京都駅に行って、ミスタードーナツから中央改札を眺める。
その京都駅の近くに、昔に設計したお店があって、ちょっと様子を見に行こうかと思う。お店の反対側の通りから様子を伺ってみると、まだ昼の早い時間だったけれどずいぶん賑わっていた。それでお店に入るのをやめる。心のどこかで、この状況を望んでいたことを自覚する。
それで、さてこれからどうしようと思ったころにはもう、すっかりと満足していて、心が落ち着いていることに気がつく。
尾道へ──inner abandoned──
6月半ば、5か月ぶりに、尾道にやってきた。
いつもと同じように向島にウィッシュを停めて、京都から積み込んできた自転車に乗り換える。そのまま渡し舟に乗り込んで尾道市街へと渡ってくる。そうやって、尾道での時間に明確なスタートをつけようとする。それから。いつもと同じマンションに荷物を置いて、いつもと同じように明確な目的を持たずにただ散策をする。そうして、ぼんやりと変化を捉えようとする。こっちだってそれなりに変わったし、そっちだって変わっているんだろう。
そうしてただひたすらに歩いていると、ふとした瞬間に、隠されようとされているものがあることに気がつく。以前よりも頑丈なやり方で塞がれた道(尾道に来るたびに強固なものになっている)、内部の惨状を隠すために外皮を補修されたあばら家。放擲された場所は、決してわれわれの生きる世界の外側にあるわけではない。しかし、われわれはそれを意識化できない。
放擲された何か──それは場所・建築・もの・身体・心など多岐にわたるのだけど──それらは往々にして、われわれの内側にある。まずは、その可能性に自覚的にならなければならない。放擲はけっして遠くのどこかにおける問題ではない。確かにすぐそこに存在しているのだけど、巧妙なあり方で見えないように、意識されないようになっている。あるいは、われわれは自ずから、その放擲された何かを意識しないこと求めてしまう。見たくないものに、無意識の蓋をしてしまう。
放擲された何か、それに自覚的でありたいと思う。そのうえで、過剰な管理や制御でも、あるいは諦めや放置でもないあり方を模索すること。ちょうどいい「ゆるさ」をともなった関与の態度が求められているのだと思う。
そして、いくつかの再会がある。
確かにあのとき同じ場所で何かを訴えかけてきた猫、喫茶店のおばちゃん、激ウマの料理とそれをつくる麻雀好きの彼。
そして尾道でもまた、いくつかの光るものを選び出す。
透明なガラスの容器、青いガラスの花瓶、灰色のグラス。入替不可能な何かへ。
再び、京都にて
そうしてまた京都へ、親しみのあるルーティンへと戻ってくる。
いくつかの物的な変化と、精神的な変化をともなって、また繭の中へ。
051724 @自宅
前から企画していた研究会の前夜、急にその気になって、ずっと前から段ボールに詰め込んだままにしていたものを部屋中に散らかしてみる。
4年前に書いていたノート、函館での行動履歴・スケッチ・テキスト・暮らしていた家の実測図面。ただ、記録するためのものたち。
気になって、その家の現在を調べてみる。外から見る分には、さほど変わっていなさそうだったのだけど、建物の中は新しいものによってすっかりと変わっていた。木目調のフローリング、5人は座れそうな大きなソファ、4人掛けのダイニングテーブル、妙に鮮やかになった黄緑のキッチン、エアコン。たしかに、あの頃よりもよっぽど快適に暮らせそうだった。もちろん、変わらないものもあった。座卓、灯油ストーブ、冷蔵庫、炊飯器、あるいは、大抵のもの。
ウェブページの説明書きを見ていると、この家はいつのまにか「古民家」ということになっていた。ページ内の中国語が妙にチラつく。あれから4年経って古民家になったのか、あるいは以前からそうだったのか。まあ、どっちでもいい。そういうことによってあの建物が残り続けるのであれば、なんだっていい。素晴らしく編集しよう。
12,3年前に買ったいくつかのCD。Green Day, My Chemical Romance, Something Corporate…。残念ながら、今は家にCDを再生する環境がないので、いくつかYoutubeで聞いてみる。少しだけ、激しいなと感じた。同時に、今でも当時のことが蘇ってくる感じがあった。手触りのある記憶が、メロディの中にもある。あるいは、それらが確かに自分の中にとどまっていて、一時的に輪郭を持ちはじめる。もちろん、足りないところがたくさんあるように思う。孔だらけの輪郭。
過ぎ去ったこと、過去のこと。遠くから見れば、大抵のものは綺麗に見える。物理的、あるいは精神的な距離においても通ずる一般論。しかし、一般論をいくら並べても人はどこにも行けない。村上春樹を読み始めたのもこの頃だったように思う。
そういえば、当時使っていたコンポやウォークマンはどこかにあるんだろうか…。どうして知らないんだろうか。
そういえば、『Whatsername』の最後のバースで、Billieがほとんど泣きじゃくっているライブ映像を見たことがあった。ずいぶんと探したのだけど見つからない(上の映像ではない)。
あらゆるなにかをつくるうえで、あたりまえに、いろんなものに影響を受けてきたし、受け続けている。だけど、その映像はひとつの重要な起点だったのかもしれないと、今になって思う。
私的なものごとのずっと奥底の方に、ほんの少しだけ他者にも共感可能な何かがある。それを見つけるために、徹底的に内省的であろうとすること。ここ数年の、ティモシー・モートンや篠原雅武への関心に通ずるもの。研究会での重要な気付き。アクチュアルで感覚的な個人的体験。
そうやって、筋道を立てて過去と現在を編集する。昔、原美術館で見た Lee Kit の展覧会を思い出す。
「人生を編集しよう。編集された人生を自分に信じ込ませるんだ。もっと細部まで編集しよう。人生は素晴らしい。」
そして四国の東端、町の中で不自然に大きくて壁のようなあのマンションに戻ってくる。その高層階、東向きの6畳の和室。紀伊水道を行き交うフェリーを眺めていた。ここではないどこか遠くの事ばかりを考えていた。物理的にも、精神的にも。
いつか液状化と津波で沈んでしまうかもしれない町。埋立地の海浜公園。遠くから見れば、大抵のものは綺麗に見える。
- January 2026 1
- June 2025 1
- April 2025 1
- February 2025 1
- January 2025 1
- December 2024 1
- November 2024 2
- October 2024 2
- September 2024 1
- August 2024 1
- July 2024 5
- June 2024 1
- May 2024 4
- April 2024 3
- March 2024 4
- February 2024 4
- January 2024 2
- December 2023 6
- November 2023 5
- October 2023 4
- September 2023 7
- August 2023 3
- July 2023 5