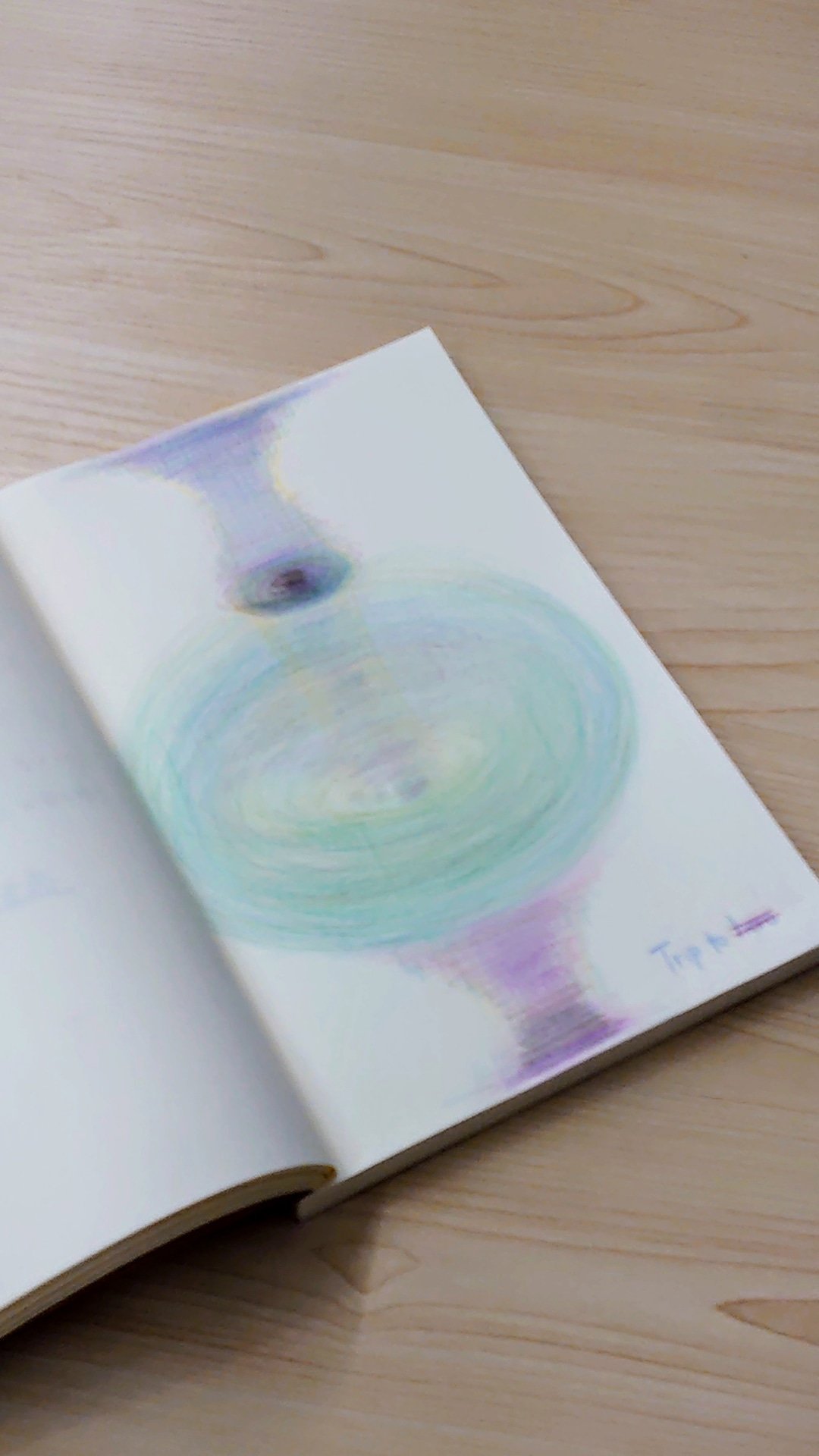近頃のこと──川湯温泉、大阪、尾道、ときどき京都
川湯温泉へ──曲がった道、入替不可能な何かへ
ひょんなことから、紀伊半島の中央部、川湯温泉へ行った。京都からトヨタのウィッシュに乗って、南へ約3時間。なにか大きな攪拌(disturbance)が起こったような場所を通り抜けて、進んでいく。
川湯温泉は当初からの目的地というわけではなかった。というのも、熊野古道に行こうと思っていて、それでなんとなく近くにある川湯温泉に泊まろうと考えていたのだ (ただ、選んだ宿は尊敬する先輩のおすすめであったから、とても楽しみにしていた)。しかし、じっさいには熊野古道に行くことはなく、ずっと川湯温泉にいた。それで結果的に、「このたびは川湯温泉に行ってまいりました」ということになるのだ。
さて、川湯温泉は紀伊半島の山間部、大塔川沿いの道(静川請川線というらしい)に宿が立ち並ぶ小さな温泉地で、ちょうどいい不自由さの中にあった。行動の選択肢を少なくして、のんびりと過ごすにぴったりの場所だった。
宿が立ち並ぶ川沿いの道は、川の蛇行に合わせて緩やかにカーブしていて、とにかく歩いていて心地がいい道だった。川の蛇行、途方もない時間をかけてつくられたその大きなリズムに、ずいぶんと小さな人間の、ちまちまと歩くリズムが響き合っていって、心が満たされていく。去年、ヨーロッパを旅するあいだに、いくつか印象的な曲がった道に出会って──ギリシャのクレタ島ChaniaやドイツのMechrnichで──それ以来、自分が曲がった道に魅力を感じていることに自覚的になった。それはそうと、川湯温泉の曲がった道は本当に素晴らしくって、そのおかげで熊野古道には行くことも無くなり、それでいてとっても素敵な時間を過ごすことができた(曲がった道については、また別の機会に書こうと思う)。
宿泊した民宿も素敵なところで、「古いが十分に手入れした建物」という宿側の自己評価に間違いはなかった。それに、素朴で豪華なごはんがとっても美味しかった。温泉はとても暑くてヘロヘロになったのだけど、その分、ビールが信じられないほど美味しく感じられた。いつの間にか、夏の気配がもうすぐそこまでやって来ていた。
ひとしきりのんびりと過ごして、京都へ戻ろうとする。帰路は東に、ひとまず熊野に出ることにする。
disturbance / message from a professor
熊野でお昼ごはんを食べようとしていたころ、とある大学の先生から連絡が来て、あれこれと仕事のお誘いをしてもらう。とってもありがたいのだけど、旅先での気持ちと嚙み合わず、妙な緊張感がある。億劫にならないうちに、プロジェクトを共同している彼と話を合わせて返事をする。京都に戻ったら、晩ごはんを食べながら話をすることになる。
昼過ぎに熊野を出てからは、伊賀を通るルートを選んだ。
それで夕方ごろに伊賀に着いて、とある窯元でとっても素敵な緑色の平皿をいただいた。たくさんの陶器が雑然と置かれた部屋の中で、そのお皿は明らかに一番魅力的だった。数多くの選択肢の中から、そういった光るものを選び出せたときには、そのときに感じた──感じさせられた──輝きの感覚がずっと残り続けるものだ。
そういうことは、買い物に限らず、より一般的な範囲で起こりうることである。人との出会いにおいても、建築の設計においても。こういうことを繰り返して、あるいはそのためにじっくりと時間をかけて、入替不可能な何かを手にしたい、つくりあげていきたいと思う。
入替不可能であること (正確には、入替可能ではないこと、かもしれない) は、5,6年前に宮台真司の議論に影響を受けて以来、ずっと意識していることなのだけど、近頃、重要なテーマとして再浮上している。それも建築、とりわけ (今設計している) 住宅、それをつくりあげていくプロセスにまつわるものとして。
もう少し一般的だったことが、おのずと建築に関わる領域に引き寄せられると、妙にワクワクする感じがある。とはいえ、この話は長くなるので、また機会にじっくりと書いて、いろんなことを少しずつ公開していきたいと思う。
入替不可能な長い家について。あるいは、私たちの家はすでに建ちはじめている。
今年はツバメの巣がよく目につく。
大阪へ──disturbance / meeting with the old friend
もう知り合って9年になる友人と、数年ぶりに会うことになった。
最後に会ったのは3年前、彼が東京にいたころだった。そのころ僕は東京にある恩師の事務所に出入りしていて、その間、友人宅を転々としていたのだけど、そのなかで彼の家にも1度だけ泊めてもらった。当時はずいぶんバタバタとしていて、夜中に事務所を引き上げて彼の家にお邪魔し、ほとんど話す時間もなく眠って、朝早くに出て行ったように思う。それからずいぶんと時間が経った。彼はこの春に転職し、今は大阪に住んでいるらしい。その旨の連絡をもらって、大阪で会うことになった。同時に、ずいぶんと久しぶりに大阪に行くことになった。
さて、長い期間を空けてから友人と会うことは、とても緊張することだ。
お互いの生きる環境が変わって──彼とは大学の学科こそ同じだったが、もともと環境は大きく違ったように思う──、それぞれがそこで過ごしてきた時間と変化を知ることになる。そのプロセスのなかで、自分が相対的に位置付けられ、自分がいったいどれだけ遠いところに来てしまったのか、それを思い知らされることになる。そしてときには、もう戻れない世界が──もはやその入口の見つからなくなった並行世界が──ほんとうに自分からは離れてしまったことを思い知る。
(他者と久しぶりに会うことに伴う諸々については、平野啓一郎『私とは何か――「個人」から「分人」へ 』での分人主義に関する議論の導入部がその理解をわかりやすく助けてくれる)
またしても、これは悲しい話ではない。
彼が予約してくれたお店の個室で焼き肉を食べながら、これまでのことを話し合って、お互いの違いを認識していく(そういえば、彼と会うときはいつも焼き肉を食べている気がする)。そのなかで大切に思われたのは、それでもなお、友人であることにおいて、適切な正直さをともなって話そうとすることだった。押し付けずに、それでいて押し付けられずに、長い時間をかけてお互いの調子を合わせてくこと。多孔性と制御の感覚はここでも役に立つ。そして、完全に重なり合うような合意を目指さないこと。一緒になることではなく、ただ一緒にいようとすること。
少し以前の関心に引き戻して考えてみる。
平野啓一郎は『本心』で、分人主義的な世界認識の先で「最愛の人の他者性」を問題化した。どれだけ長い時間をともにしても──あるいは長い時間をともにするがゆえに──最愛の人が他者であるという事実からは逃れられない。まあ、彼が最愛の人であるかどうかは置いておいて、平野が『本心』で示した他者の他者性と向き合う誠実さというのは、20代の後半に差し掛かって、それぞれの人生が大きく逸れ合っていく自分とその周囲の人との関係において、あらためて重要なことになっている。身近な人であるほど、長く時間をともにするほど、難しくなることというのがある。それでも、なんとか自覚的になって、できる限り誠実でありたいと思う。
そういえば、『本心』は映画化するそうです。監督は石井裕也さんで、主演は池松壮亮さん。かねてから、池松壮亮さんは代えがたい魅力を持った素敵な俳優だと感じています。そういう人ってそう多くはいないんだけど…。
彼と別れてから、梅田の喫茶店に入って会話の内容を反芻する。自分なりに書き起こして保存する。そして、梅雨が明けたころに会話を再開する。楽しみなことが増えた。
京都にて
ときどき、京都を離れてどこかに行く。そこではあたりまえだけど、良いことと悪いことのどちらもが起こって、それによって少し自分が攪拌される。その後に、少しの気付きとともに京都に戻ってきて、それまでの長い時間をかけてつくりあげてきたルーティン、その繭の中で、親しみのあるリズムに再び調子を合わせていく。
自宅のキッチンで、時間をかけてオリーブオイルに、にんにく・ベーコンの香りをうつす。そのルーティンの具体的な部分――たとえば、火や食材の様子――に注意深くなって、じっくりと、美味しいと感じられるパスタをつくる。そうしていると、脇にある建具の隙間から、隣地での変化が入ってこようとしていることに気がつく。そしてそれを受け入れようとする。今年も紫陽花が咲いている。天窓に入ってきては出ていく雲を眺めて、いつもの猫たちに会いに行く。悲しいことに、いつの間にか会えなくなった猫がいて、一方で、最近になってよく会うようになった猫がいる。先日連絡をくれた大学の先生たちと少し緊張感のある食事兼打合せをし、翌日には気心知れた友人たちとプロジェクトの打ち上げと題して川辺でピクニックをし、素敵な居酒屋でのんびりと過ごす。
安定したルーティンの中で、とにかく具体的なことに注意深くなろうとする。そうして、変化を選択的に受容する。
ときどき、そのルーティンの中に、新しい入口と出口が生じていることに気がつく。
京都留学の終わりが近づいてきた友人と会って、タイ料理を食べる。もう4年ほど定期的に会っている。多くのことを話したし、多くの大切なことを教えてもらった。ずっとここに居てほしいように思うけれど、彼には戻るべきホームタウンがあって、仕事とポストが待っている。彼は、僕がタイに行けるよう準備してくれるという。それで、たまに一緒に仕事をしようと言ってくれる。そんなことができたら、とっても幸せなことなのだろうと思う。
あるいは、またひとり、友人を京都から送り出す。同じ研究室で過ごして、その後、共同で仕事をすることをとおして、多くの感覚と言語を共有したように思う。けっしてひとりではたどり着けなかった現状に感謝して、そしてわれわれの素晴らしい未来を願って、いつもの素敵な居酒屋で晩餐をともにする。
あるいは、つくったことがないご飯をつくる、つくってもらう。苦手だと思っていたタイカレーを自分が美味しいと感じることに気がつく。タイカレーにビールという新しい夏の風物詩が自分の世界に入ってくる。
なんだかふと、人の多いところに行きたくなって、休日の京都駅に行って、ミスタードーナツから中央改札を眺める。
その京都駅の近くに、昔に設計したお店があって、ちょっと様子を見に行こうかと思う。お店の反対側の通りから様子を伺ってみると、まだ昼の早い時間だったけれどずいぶん賑わっていた。それでお店に入るのをやめる。心のどこかで、この状況を望んでいたことを自覚する。
それで、さてこれからどうしようと思ったころにはもう、すっかりと満足していて、心が落ち着いていることに気がつく。
尾道へ──inner abandoned──
6月半ば、5か月ぶりに、尾道にやってきた。
いつもと同じように向島にウィッシュを停めて、京都から積み込んできた自転車に乗り換える。そのまま渡し舟に乗り込んで尾道市街へと渡ってくる。そうやって、尾道での時間に明確なスタートをつけようとする。それから。いつもと同じマンションに荷物を置いて、いつもと同じように明確な目的を持たずにただ散策をする。そうして、ぼんやりと変化を捉えようとする。こっちだってそれなりに変わったし、そっちだって変わっているんだろう。
そうしてただひたすらに歩いていると、ふとした瞬間に、隠されようとされているものがあることに気がつく。以前よりも頑丈なやり方で塞がれた道(尾道に来るたびに強固なものになっている)、内部の惨状を隠すために外皮を補修されたあばら家。放擲された場所は、決してわれわれの生きる世界の外側にあるわけではない。しかし、われわれはそれを意識化できない。
放擲された何か──それは場所・建築・もの・身体・心など多岐にわたるのだけど──それらは往々にして、われわれの内側にある。まずは、その可能性に自覚的にならなければならない。放擲はけっして遠くのどこかにおける問題ではない。確かにすぐそこに存在しているのだけど、巧妙なあり方で見えないように、意識されないようになっている。あるいは、われわれは自ずから、その放擲された何かを意識しないこと求めてしまう。見たくないものに、無意識の蓋をしてしまう。
放擲された何か、それに自覚的でありたいと思う。そのうえで、過剰な管理や制御でも、あるいは諦めや放置でもないあり方を模索すること。ちょうどいい「ゆるさ」をともなった関与の態度が求められているのだと思う。
そして、いくつかの再会がある。
確かにあのとき同じ場所で何かを訴えかけてきた猫、喫茶店のおばちゃん、激ウマの料理とそれをつくる麻雀好きの彼。
そして尾道でもまた、いくつかの光るものを選び出す。
透明なガラスの容器、青いガラスの花瓶、灰色のグラス。入替不可能な何かへ。
再び、京都にて
そうしてまた京都へ、親しみのあるルーティンへと戻ってくる。
いくつかの物的な変化と、精神的な変化をともなって、また繭の中へ。